State of AI Report 2025とはなにか?
毎年この時期になると、私が楽しみにしているレポートがあります。Nathan Benaich氏が発行する「State of AI Report」です。
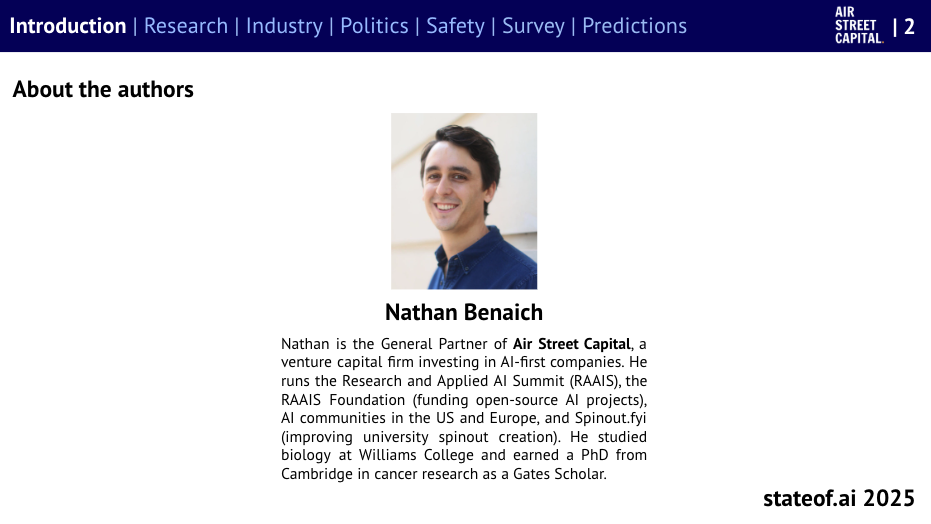
2025年版が10月9日に公開されたのですが、今年の内容を読んで、どうやらAIの世界が新しいフェーズに入ってきたような気がしてきました。
ちなみに、昨年の内容は以下の記事でまとめています。
このレポートは、過去1年間のAIの進化を6つの視点から整理しています。技術的なブレークスルーを追う「リサーチ」、実際のビジネスへの影響を見る「産業」、規制や地政学を扱う「政治」、リスク管理に焦点を当てる「安全性」、そして1,200人以上のAI実務者への「ユーザー調査」、さらには今後12ヶ月の「予測」です。
特に印象的だったのは、2025年が「推論能力が現実のものとなった年」と位置付けられている点です。OpenAI、Google、Anthropic、そしてDeepSeekといった企業が、複雑なタスクを推論できるシステムを次々と発表しました。また、ビジネス面では大手AIラボや主要企業が年間約200億ドルの収益を上げるなど、誇大広告ではなく実際の成果が見え始めています。
一方で、気になるデータもあります。サイバー攻撃能力が5ヶ月ごとに倍増しているという報告や、犯罪者がAIエージェントを使って企業に侵入するケースも出てきているそうです。技術の進化と、それに伴うリスクの両面を見ていく必要があるのではないでしょうか。
ユーザー調査の結果も興味深いものでした。専門家の95%が仕事や家庭でAIを使用し、76%が自己負担でAIツールの利用料を支払っているとのことです。AIがすでに私たちの日常に深く入り込んでいることを示すデータだと思います。
本記事では、このレポートから見えてきたAIの現状と、これから私たちが向き合うべき変化について、一緒に考えていきたいと思います。技術の進歩を単なる情報として受け取るのではなく、それが私たち自身の働き方や生活にどう影響するのか、具体的にイメージしながら読み進めてみてください。
2025年AI総括:「推論の実用化」と「物理世界の制約」という現実

冒頭に述べた通り、今年を「推論(reasoning)が現実になった年」と定義しました。これは、AIが単にパターンを認識するだけでなく、「考えてから答える」能力を本格的に社会実装し始めたことを意味します。
どうやら、AIは空想の段階を終え、私たちの仕事や経済、そして国家戦略にまで深く根を張る「インフラ」へとその姿を変えつつあるようです。しかし、その輝かしい進化の裏側で、私たちは電力や土地といった、極めて物理的な制約という現実にも直面し始めています。ここからは、同レポートを基に、2025年のAIが示した二つの大きな潮流を読み解いていきたいと思います。
また、本レポートでは、昨年度の予測に対する答え合わせも行っているため、まずはそこから時系列に見ていきましょう。
2024年の予測はどこまで当たったのか?
では、昨年のレポートが掲げた予測がどうなったか、答え合わせから始めましょう。未来を正確に予測することの難しさと、AIの進化がどの方向に進みやすいのかが見えてくるのではないでしょうか。
| 予測項目 | 結果 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| コーディング能力のない人物が単独で作成したアプリやウェブサイトがバイラルになる(例:App Storeトップ100) | YES | Bubbleで完全構築のFormula BotがRedditでバズり一晩で10万人訪問、3ヶ月で30,000ドル売上 |
| フロンティア・ラボが、訴訟が裁判に達し始めた後、データ収集慣行に意味のある変更を実施する | YES | 著者と15億ドルで和解・著作物削除・合法取得書籍へ移行、OpenAIがFutureと有料パートナーシップ締結 |
| OpenAIのo1に代わるオープンソースの選択肢が、さまざまな推論ベンチマークでそれを上回る | YES | DeepSeek R1がAIMEやMATH-500等の主要ベンチマークでo1を上回る |
| チャレンジャーがNVIDIAの市場地位に意味のある打撃を与えることに失敗する | YES | NVIDIAが依然支配的・競合が大きなシェア獲得できず |
| AI科学者によって生成された研究論文が、主要なMLカンファレンスまたはワークショップで採択される | YES | AI生成論文「The AI Scientist-v2」がICLRワークショップに採択 |
| EU AI法(AI Act)の初期の施行は、議員がやりすぎを懸念した後、予想よりも緩やかになる | NO | 義務は段階的導入、自主的GPAI規範スタートとしつつも“緩やか”に施行された |
| 人型ロボットへの投資レベルは、企業がプロダクト・マーケット・フィットの達成に苦慮するため、落ち込む | NO | 投資は減らず2025年に30億ドル(前年比増) |
| Appleのオンデバイス研究からの強力な結果が、パーソナル・オンデバイスAIをめぐる勢いを加速させる | NO | Apple Intelligenceで多くのモデルがオンデバイス展開、業界の流れを後押し・AI対応スマホ出荷増 |
| GenAIベースの要素とのインタラクションを中心としたビデオゲームが、ブレイクアウトの地位を達成する | NO | まだ達成していない |
| 主権国家からの100億ドル以上の投資が、米国の主要なAIラボへの国家安全保障上の審査を引き起こす | – | HUMAINの100億ドルVCファンドやUAEのStargateインフラ等はインフラ提携であり、ラボの直接投資過半数ではない |
この結果を見て、ある傾向に気づかないでしょうか。ソフトウェアやアルゴリズムの世界、つまりデジタルで完結する領域の進化は、私たちの予測通りか、それ以上に早く進んでいます。
一方で、ヒト型ロボットやゲームといった、物理世界や複雑な人間とのインタラクションが絡む領域では、まだブレイクスルーに時間がかかっているように見えます。この傾向こそ、2025年のAIを象徴する二つの潮流へと繋がっていくのです。
潮流1:「推論」が実用化され、ビジネス価値を生み始めた
今年のAIにおける最大のトピックは、間違いなく「推論能力の実用化」でしょう。AIが単に情報を検索して要約するだけでなく、与えられた課題に対して複数のステップを考え、計画を立て、検証しながら答えを導き出す「思考のプロセス」を製品レベルで実装し始めました。
この進化は、ビジネスの現場に大きなインパクトを与えています。一部の主要なAIラボは、合算で数十億ドルから200億ドル規模の収益を上げる段階に入りました。AIはもはや研究開発の対象ではなく、明確な利益を生み出す事業の柱になりつつあるのです。この背景には、AIの能力そのものの向上はもちろん、AIをより安価に、より速く提供するための技術革新があります。
潮流2:競争の主戦場は「物理世界の制約」へ
しかし、この輝かしい進化は、新たな、そして極めて現実的な課題を浮き彫りにしました。それが「物理世界の制約」です。AIモデルの性能が向上するにつれて、その学習と運用に必要な計算資源、そしてそれを支える電力と土地の需要が爆発的に増加したのです。
レポートでは、数ギガワット(GW)級の電力を消費する巨大なデータセンターの建設計画が次々と立ち上がり、電力供給、送電網、そしてデータセンター建設に対する地域住民の合意(NIMBY問題)が、企業のAI戦略を左右する重要な要素になったと指摘されています。
どうやらAIの競争は、もはやアルゴリズムの優劣だけで決まる時代ではなくなったようです。潤沢な電力を確保できるか。広大な土地を用意できるか。国家レベルのインフラ戦略が、企業の、そして国のAI競争力を直接的に規定する。そんな時代が、もう始まっているのかもしれません。

2025年は、AIがその知性を現実世界の問題解決に向け始めた記念すべき年であると同時に、その知性を動かすための物理的なエネルギーと場所を、私たち人間社会と奪い合い始めた年でもありました。
では、この「思考するAI」は具体的にどのような技術で実現され、ビジネスの現場でどのように収益を生んでいるのでしょうか。そして、電力やインフラという新たな制約は、産業界にどのようなジレンマをもたらしているのでしょうか。次のセクションでは、研究の最前線とビジネスの現実を、さらに詳しく見ていきたいと思います。
「思考するAI」は儲かるのか?研究の最前線とビジネスの現実

前のセクションでは、2025年のAIが「推論の実用化」という新たなステージに入った一方で、電力や土地といった「物理世界の制約」に直面し始めたという二つの大きな潮流を見ました。
では、その「思考するAI」とは具体的にどのような技術で、どのようにしてビジネスの世界で莫大な利益を生み出し始めたのでしょうか。そして、その輝かしい成長の裏には、どのような現実的なジレンマが横たわっているのでしょうか。ここでは、研究の最前線からビジネスの現場までを貫く光と影を、さらに詳しく見ていきたいと思います。
「考えてから答える」AIの誕生
2025年、AI業界の競争軸を根本から変えたのは、「考えてから答える(think-then-answer)」という一連の技術でした。これは、思考の連鎖(Chain-of-Thought)といった手法が、実験室レベルから私たちが日常的に使う製品へと本格的に導入されたことを意味します。
OpenAIの「o1」が火をつけたこの競争は、中国のDeepSeekがリリースした「」などがすぐに追随し、主要なAIラボが互いにリードを奪い合う激しい開発競争へと発展しました。どうやらAIは、単なる物知りのアシスタントから、複雑な問題解決を共に進める思考のパートナーへと、その役割を進化させたようです。
さらに、研究の最前線は「世界モデル」という新たな領域にも踏み込んでいます。これは、音響や物理法則、対話までを統合した仮想世界をシミュレートする技術です。もはやAIはテキストや画像を生成するだけでなく、ロボットの訓練や創薬の初期探索といった、現実世界を模倣し、そこで実験を繰り返すことまで可能にし始めています。
利益を生むAI、そのカラクリ
では、こうした研究成果は、どのようにしてビジネス上の利益に結びついたのでしょうか。答えは明快です。「思考するAI」は、これまで人間にしかできなかった高度な知的労働を、圧倒的な低コストで代替・支援できるからです。
その結果は、数字にもはっきりと表れています。一部の主要なAIラボは、合算で数十億ドルから最大で200億ドル規模の年間収益を上げるまでになりました。企業への導入も爆発的に進んでいます。Rampの調査によれば、AIツールに費用を支払う米国企業の割合は、2023年1月のわずか5%から、2025年9月には43.8%へと急上昇しています。
この背景には、能力と価格の劇的な改善があります。レポートによれば、AIモデルの能力対価格の比率は、約6〜8ヶ月ごとに倍増しているといいます。つまり、同じコストで手に入るAIの知性は、半年ごとに倍になっている計算です。これにより、多くの企業がAI導入のROI(投資対効果)を出しやすくなったことが、この急成長の大きな原動力になっているのではないでしょうか。
輝かしい成果の裏にある3つのジレンマ
しかし、このサクセスストーリーは、産業界に新たな、そして根深いジレンマをもたらしています。
評価のジレンマ:AIは本当に賢くなったのか?
推論モデルの性能競争が激化する一方で、その評価はますます難しくなっています。レポートが指摘するのは「ベンチマーク汚染」という深刻な問題です。
これは、モデルが評価用のテストデータを事前に学習してしまい、見かけ上のスコアだけが高くなる現象を指します。実際、多くの強化学習ベースの手法は、再現性評価を行うと報告された性能から6〜17%も低下する例が確認されており、「見かけ上の進歩」と真の能力向上を区別することが極めて困難になっているのです。
権利のジレンマ:誰のデータで、誰が儲けるのか?
AIの学習には膨大なデータが必要ですが、そのデータの権利を巡る問題が顕在化しています。象徴的だったのが、Anthropicが書籍の著者らとの著作権訴訟で15億ドルという巨額の和解金を支払うことで合意した一件です。
AIが生み出す価値の源泉である学習データが、同時に莫大な法的・金銭的リスクにもなっている。この現実は、AIビジネスの収益構造そのものを揺るかしかねません。最近では訴訟から協業へと潮目が変わり、700以上のニュースブランドがAI企業と契約を結ぶ動きも見られますが、権利構造の複雑さは増すばかりです。
インフラのジレンマ:AIの頭脳を動かす「体」が足りない
そして、最も物理的で避けがたい問題がインフラです。AIの思考が高度化すればするほど、その頭脳を動かすためのGPUと、それを冷やすための電力が必要になります。
レポートでは、数ギガワット級のデータセンター建設が現実のものとなる一方、電力供給や送電網のキャパシティ、さらには地域住民の反対運動(NIMBY)が、AI産業の成長を阻む物理的な足枷となり始めたと警告しています。
「思考するAI」は、確かに儲かり始めています。しかし、その成長は、私たちがその「賢さ」を正しく測る物差しを持ち、その「知識」の源泉である権利関係を整理し、そしてその「活動」を支える物理的なエネルギーを確保できるかにかかっている。どうやら、AIの未来は、アルゴリズムだけでなく、こうした現実世界の制約とどう向き合うかにかかっているようです。
特に、インフラを巡る問題は、もはや一企業の努力で解決できるレベルを超え、国家間のエネルギー戦略や地政学的な競争へと直結しています。次のセクションでは、AI覇権がコードではなく、電力で決まる時代の実態をさらに深く掘り下げていきます。
AI覇権はコードではなく電力で決まる:米中新冷戦とソブリンAIという国家戦略

前のセクションで、AI産業の急成長が「インフラのジレンマ」という物理的な壁に突き当たり始めたことを見ました。どうやら、AIの競争はもはや個々の企業のアルゴリズム開発競争ではなく、国家の威信をかけた総力戦へとその姿を変えつつあるようです。
もはや主役はコードを書くエンジニアだけではありません。電力網を設計する技術者、広大な土地を確保する交渉人、そして国家戦略を立案する政治家たちが、AIの未来を左右する新たなキープレイヤーとして登場してきた気がします。ここでは、AIを巡る地政学の最前線で何が起きているのかを、さらに深く見ていきましょう。
三極化する世界のAI国家戦略
かつてAI開発の最前線はシリコンバレーに集中していましたが、2025年現在、世界は大きく三つの戦略に分かれつつあります。それは、米国、中国、そして潤沢なオイルマネーを背景に台頭する湾岸諸国などです。
米国の「America-first AI」戦略
米国は、トランプ政権下で「America-first AI」という攻撃的な国家戦略を鮮明にしています。これは単に国内のAI産業を守るという話ではありません。5000億ドル規模ともいわれるAIインフラ計画「Stargate Project」に代表される巨大投資を通じて、計算資源そのものを支配しようという強い意志を感じます。
さらに、ハードウェアからモデル、ソフトウェアまでをパッケージ化して同盟国に提供する「AIスタック輸出」構想は、まるで21世紀版のマーシャル・プランのようです。これは、米国の技術的優位性を、世界のAIインフラの「OS」として根付かせることで、長期的な覇権を狙う壮大な戦略ではないでしょうか。
中国の「オープンウェイト」という名のソフトパワー
一方、米国からの厳しい半導体輸出規制に直面する中国は、全く異なるアプローチを取っています。彼らは国産チップの開発を急ぐと同時に、「オープンウェイト(open-weight)」、つまりオープンソースのAIモデルを積極的に推進しています。
Alibabaの「Qwen」やDeepSeekといった中国発のモデルが、かつて市場を席巻したMetaのLlamaを凌ぐ勢いで開発者コミュニティに浸透しているのは、その象徴です。これは、規制で閉じられた扉を、オープンな生態系を作ることで迂回し、世界中の開発者を味方につけるという、したたかなソフトパワー戦略だと考えられます。
第三極を目指す「ソブリンAI」
そして、この米中対立の構図に割って入るのが、UAE(アラブ首長国連邦)などの湾岸諸国です。彼らは「ソブリンAI」という旗印を掲げ、オイルマネーを元手に自国でAI技術を管理・運用しようとしています。これは、データ主権を守り、デジタル経済における自律性を確保するための国家戦略です。
NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏もこの動きを後押ししており、2025年には200億ドルを超えるソブリンAI関連の収益を予測しているほどです。しかし、その実態は海外の技術や人材に大きく依存しているケースも多く、「ソブリンウォッシング」ではないかとの指摘もあります。
新たな戦場は「電力」と「土地」
こうした国家間の壮大な戦略がぶつかり合う主戦場は、もはやサイバー空間だけではありません。驚くべきことに、それは私たちの足元にある「電力網」と「土地」という、極めて物理的な領域に移ってきているのです。
AIの性能向上は、指数関数的に増大する計算量を必要とします。その結果、Anthropicは2028年までに5GW(ギガワット)規模のトレーニングクラスターが必要になると予測しています。これは、もはや一つの大都市の電力消費量に匹敵する規模です。
この「電力喰い」のAIを動かすため、世界中で巨大データセンターの建設ラッシュが起きています。しかし、それは新たな問題を生み出しました。
米国のAIスーパーコンピュータ容量は世界の約75%を占めるなど計算能力では他を圧倒していますが、その足元では電力不足が深刻なボトルネックになりつつあります。一方で、中国は新たな発電容量の追加で米国を上回っており、長期的なAI競争において静かな、しかし決定的な優位性を築いているのかもしれません。
さらに、データセンター建設は、地域住民との軋轢という新たな火種を生んでいます。レポートでは、データセンターに対する住民の反対運動(NIMBYism)は、2026年の中間選挙や州知事選挙に影響を与える可能性があると予測されています。AIの未来が、技術的なブレークスルーだけでなく、地域社会との地道な合意形成にかかっているというのは、なんとも皮肉な話ではないでしょうか。
どうやら私たちは、AIの進化を語る際に、アルゴリズムやモデルの性能ばかりに目を奪われがちだったのかもしれません。しかし、2025年の現実は、AI覇権の行方が、電力網を制し、広大な土地を確保し、社会的な合意を取り付けた国家や企業の手に委ねられつつあることを示しています。この壮大な国家間のゲームは、最終的に私たちの生活や仕事にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
次のセクションでは、こうしたマクロな地政学的な変化の渦中で、現場のユーザーたちがAIをどのように使いこなし、その進化に何を感じているのか、そのリアルな声に耳を傾けてみたいと思います。
現場は熱狂、未来はどうなる?ユーザー動向と2026年への10大予測

これまでのセクションで、私たちはAIを巡る産業の構造変化や、国家間の壮大な地政学ゲームを俯瞰してきました。しかし、そうしたマクロな変化の渦中で、私たちの日常、つまり「現場」では一体何が起きているのでしょうか。
国家がAI覇権を競い、企業が巨額の投資を行う一方で、個々のユーザーはAIをどう使いこなし、その進化に何を感じているのか。どうやらその熱狂は、私たちの想像をはるかに超えているようです。
95%が利用、76%が自腹。AIは「空気」になった
State of AI Report 2025に掲載された1,183人のAI利用者を対象とした調査結果は、衝撃的と言えるかもしれません。回答者の95%以上が仕事と私生活の両方でAIを利用しており、さらに驚くべきことに、そのうち76%が自費でAIサービスに課金しているというのです。
これは、AIがもはや一部の技術好きのためのおもちゃではなく、日々の業務や生活に不可欠な「道具」として、個人の財布から投資する価値があると認識されていることを示しています。
しかも、その効果は絶大です。実に92%が生成AIサービスによる生産性向上を報告し、そのうち47%は「著しく向上した」と感じているようです。従来の検索エンジン、特にGoogleの代わりにAIを使うという声も多く、私たちの情報収集のあり方が根本から変わりつつある気がしてきました。
しかし、この熱狂の裏には現実的な課題も存在します。AIを組織でスケールさせる際の障壁として、多くの人が「システムを確実に動かすための初期設定時間」「データプライバシーへの懸念」「専門知識の不足」などを挙げています。
AIが強力なエンジンであることは誰もが認めるところですが、そのエンジンを安全かつ効率的に組織の車体に組み込むには、まだ整備すべき点が多く残されている、ということではないでしょうか。
光が強ければ、影もまた濃くなる
ユーザーの熱狂が広がる一方で、AIの強力な能力は、悪意ある者たちにとっても魅力的な道具となります。レポートは、AIの安全性が、かつてのような「人類の存亡をかけた理論的な議論」から、より現実的で差し迫った「サイバー攻撃」や「生物化学兵器への悪用」といった実務的なリスクへと重心を移していることを警告しています。
特にサイバーセキュリティの領域では、その進化速度は驚異的です。ある研究によれば、攻撃的なサイバーセキュリティにおけるAIのタスク完了能力は、わずか5ヶ月ごとに倍増しているといいます。
実際に、北朝鮮の工作員がClaudeを利用してFortune 500企業に侵入した事例も報告されており、AIを使ったハッキング、いわゆる「Vibe Hacking」が現実の脅威となっています。
こうした状況を受けて、AIの安全性を確保するための新しい概念として「監視可能性(monitorability)」が重要視され始めています。これは、AIが内部で何を行い、どのような判断を下したのかを、人間が後から追跡・監査できるように設計すべきだという考え方です。
AIの思考プロセス(Chain-of-Thought)を監視することで、意図しない行動や悪意ある試みを検出できる可能性が示されています。しかし、これは簡単なことではありません。透明性を高めようとすると性能が落ち、性能を追求すると中身がブラックボックス化するというトレードオフ、いわば「監視可能性税」を支払う覚悟が求められるのかもしれません。
未来への羅針盤:2026年に向けた10大予測

さて、熱狂する現場と、忍び寄る影。この混沌とした状況の中で、私たちはどこへ向かうのでしょうか。レポートは、次の12ヶ月に起こりうる変化として、10の具体的な予測を提示しています。これは、私たちが来年に向けて何を考え、備えるべきかの羅針盤となるはずです。
ビジネスと社会の変革
どうやら、AIエージェントが私たちの経済活動に直接的なインパクトを与える未来は、もうすぐそこまで来ているようです。
- エージェントによる買い物が本格化:主要な小売業者が、AIエージェントによる決済がオンライン売上の5%を超えたと報告し、AIエージェント向けの広告費は50億ドルに達する。
- AIネイティブなエンタメの誕生:リアルタイムでインタラクティブに生成されるビデオゲームが、ゲーム配信プラットフォームのTwitchで年間最も視聴されるタイトルになる。
- クリエイティブ分野での衝突:AIを大々的に活用して制作された映画や短編作品が、観客から大きな称賛を得ると同時に、激しい反発も招く。
技術と研究のブレークスルー
AI自身が新たな知識を発見し、技術覇権の地図を塗り替える可能性が示唆されています。
- AI科学者の登場:オープンエンド型のエージェントが、仮説立案から実験、論文執筆までを自律的に行い、意味のある科学的発見を成し遂げる。
- 中国の躍進:中国のAIラボが、LMArenaのような主要な性能リーダーボードで、米国ラボのモデルを追い越す。
- オープンソースへの回帰:主要なAIラボが、現政権の支持を得るために、再びフロンティアモデルのオープンソース化に力を入れる。
政治と地政学の新たな火種
AIの進化は、国際関係や国内政治にも新たな緊張関係をもたらしそうです。
- AIが安全保障の議題に:ディープフェイクやエージェント主導のサイバー攻撃が、初のNATO/UN緊急討議を引き起こす。
- 新たな外交戦略「AI中立性」:一部の国がソブリンAIの開発を断念、あるいは失敗し、「AI中立性」が新たな外交政策として浮上する。
- 物理インフラを巡る対立:データセンターへの近隣住民の反対運動が米国を席巻し、2026年の選挙に影響を与える。
- 規制を巡る政治的衝突:トランプ大統領が州レベルのAI法を禁止する大統領令を出すも、最高裁判所によって違憲と判断される。
これらの予測が示唆するのは、AIがもはや技術の世界に閉じこもってはいられない、ということです。ビジネス、科学、政治、そして私たちの文化そのものと深く結びつき、良くも悪くも社会を根底から揺さぶる力となりつつあります。
この記事を通じて、私たちは2025年のAIを巡る壮大な物語を旅してきました。「推論の実用化」という技術的な夜明けから、産業界の熱狂とジレンマ、そして国家間の覇権争い、最後に私たちユーザー一人ひとりの手元での普及まで。その全てが、AIが私たちの世界をいかに急速に、そして不可逆的に変えつつあるかを物語っています。
未来は不確かですが、確かなことが一つあります。それは、私たちがもはやAIの進化を「対岸の火事」として眺めていることはできない、ということです。提示された10の予測は、単なる未来の出来事リストではありません。それは、私たちがこれから直面するであろう変化の波であり、その波にどう乗りこなすかを問う、私たち一人ひとりへの挑戦状ではないでしょうか。
調査手法について
こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。
調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。
また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。
ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。
また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai







コメント