「AIが設計した薬、ヒトで効いた」

どうやら、生成AIが新しい分子を設計するという話は、「コンピューター上のシミュレーションで良いスコアが出た」という段階から、「実際にヒトで効果が確認された」という、全く新しい次元に突入したようです。この変化を象徴するのが、AI創薬企業Insilico Medicine社が開発した「Rentosertib」という薬の事例ではないでしょうか。
AIがゼロから病気の原因となるタンパク質(標的)を見つけ出し、それに対して効果のある分子構造を設計。その薬が、治療法が限られている難病「特発性肺線-維症」の患者さんを対象とした臨床試験で、肺機能の改善を示すという有望な結果を出したのです。
具体的には、12週間の投与で、プラセボ(偽薬)を投与された患者グループの肺機能が平均で20.3mL低下したのに対し、Rentosertibを投与されたグループでは平均98.4mLも改善したというのですから、驚きです。この成果は、権威ある医学雑誌Nature Medicineにも掲載されました。
この一件が持つ意味は、単に「AI創薬の成功事例が一つ増えた」という話に留まらないと、私は感じています。これは、これまで期待や可能性として語られてきた分子生成AIが、いよいよ「臨床価値」という現実的な成果を問われる“実装”フェーズへと足を踏み入れた、決定的なサインなのかもしれません。
熱狂する市場と、その視線の先にあるもの
この「実装」への期待は、市場の熱気にもはっきりと表れています。AI創薬市場の規模は、ある調査では2023年の約15億ドルから2030年には203億ドルへと急拡大すると予測され、また別の調査では2024年の17.1億ドルから2030年には85.2億ドルに達するとも言われています。予測に幅があるものの、年平均30%近い驚異的な成長が見込まれている点は共通しています。
なぜ、投資家や巨大製薬企業はこれほどまでにこの分野に注目するのでしょうか。それは、AIが創薬における探索フェーズの時間と試行回数を劇的に削減し、これまで10年以上かかっていた開発期間を数年単位に短縮する可能性を秘めているからです。Insilicoの事例も、標的発見から臨床試験の開始までをわずか30ヶ月未満で達成したと報告されており、AIの持つポテンシャルを裏付けています。
しかし、Insilicoの成功がもたらした最も大きな変化は、この分野を見る「評価の軸」そのものを変えたことにあるように思います。これまでは、AIモデルがいかに賢いか、どれだけユニークな分子を設計できるか、といった「技術の性能」が主な関心事でした。しかし、これからは違います。AIが設計した薬が、本当に患者を救うのか、臨床的な価値を生み出せるのか。市場の関心は、その一点に集約されつつあるのです。
もちろん、過度な楽観は禁物です。AIが設計した薬の候補が、臨床試験の段階で開発中止になるケースも存在します。例えば、Exscientia社が関わったDSP-1181という候補薬は、安全性以外の理由で開発が中止されました。AIはあくまで創薬の成功確率を高めるための強力なツールであり、臨床開発の壁を魔法のように消し去るわけではありません。
それでもなお、時代は明らかに次のステージへと進みました。生成AI×分子生成は、もはや単なる技術デモではなく、現実の医療を変えるための具体的な「実装」の時代を迎えたのです。では、この新しい時代の中で、お金はどこに流れ、どのような企業が勝ち残ろうとしているのでしょうか。次のセクションでは、具体的な資金調達の事例を深掘りしながら、そのトレンドを読み解いていきたいと思います。

お金の流れで読むトレンド:資金は「AI+実験自動化」を持つ強者へ

前のセクションで見たように、Insilico Medicine社の臨床成功は、分子生成AIが「実装」の時代に入ったことを市場に強く印象付けました。この変化は、投資家や製薬大手といった「賢いお金」の流れにも、明確な方向性を与えているように思えます。もはや、「面白いAIモデルを作りました」だけでは不十分。では、実際に資金はどこへ、どのような能力を持つ企業へと向かっているのでしょうか。
近年の大型資金調達や提携事例を分析すると、どうやら市場の評価軸は二つの異なる、しかし本質的には同じ方向を向いた戦略に収斂しつつあるようです。
二極化する生存戦略
一つ目の戦略は、巨大製薬企業とがっちり手を組む「協業型プラットフォーマー」としての道です。その代表例が、PostEra社と製薬大手Pfizer社の提携でしょう。両社はAI創薬のコラボレーションを拡大し、その協業枠は総額で6.1億ドル(約900億円)にも達すると発表されています。
PostEraは自社のAIプラットフォームを提供し、Pfizerが持つ膨大なデータと研究開発インフラと組み合わせることで、創薬プロセスの加速を目指すモデルです。これは、AIスタートアップが臨床開発や販売といった莫大なリスクとコストのかかる部分をパートナーに委ね、技術提供に特化することで早期に収益を上げる、現実的な戦略と言えるでしょう。
そしてもう一方の極にあるのが、自社で創薬の全工程を完結させようとする「垂直統合型パイプライン企業」です。2024年にシリーズA-1ラウンドで約2,460万ドルを調達したDeepCure社は、このモデルの好例です。
彼らはAIで分子を設計するだけでなく、自社でパイプライン(新薬候補の製品群)を構築し、臨床試験へと進めることを目指しています。成功すれば莫大なリターンが期待できる一方で、創薬の全リスクを自社で負う、野心的な挑戦です。
成功モデルの共通分母「実験閉ループ」
一見すると正反対に見えるこの二つの戦略ですが、その根底には驚くほど共通した成功要因が横たわっています。それは、AIによる設計と、物理世界での実験を高速で繋ぐ「実験閉ループ」の構築です。
DeepCure社が投資家から評価されているのは、単に優秀なAIエンジンを持っているからだけではありません。彼らが「生成AI」と「物理・構造解析を組み合わせた設計」に加えて、「ロボット駆動の合成プラットフォーム(自動合成)」を統合している点が決定的に重要なのです。
AIが設計した分子を、ロボットが即座に合成し、その結果を評価して、またAIの設計にフィードバックする。この「設計→合成→評価」のサイクルを、人間を介さずに高速で回せる能力こそが、彼らの競争力の源泉となっています。

これは、投資家の視点が「AIがどれだけ賢いか」から「AIの予測を、いかに早く、確実に、物理世界の分子として検証できるか」へと完全にシフトしたことを物語っています。計算上の有望さ(in-silico)だけでなく、実験室(wet lab)での実証能力がなければ、もはや資金は集まらないのです。
この傾向は、PostEraのような協業型モデルにも当てはまります。彼らがPfizerのような巨大企業と組むのは、Pfizerが持つ世界トップクラスの実験設備や、長年蓄積された臨床データを活用できるからです。結局のところ、ビジネスモデルが協業型であれ垂直統合型であれ、AIと実験インフラをいかにシームレスに連携させるかが、成功の鍵を握っていると言えるでしょう。
お金の流れは、市場が「AI単体」の価値ではなく、「AI+実験自動化」というパッケージの価値を評価し始めたことを明確に示しています。では、この強力なエンジンを動かしているAI技術そのものは、今どのような進化を遂げているのでしょうか。次のセクションでは、化学言語モデルからAIによる遺伝子編集まで、その技術の最前線に迫ってみたいと思います。
技術進化の最前線:化学言語モデル(TamGen)からAI遺伝子編集(OpenCRISPR-1)まで

前のセクションでは、分子生成AIの領域で「賢いお金」がAIと実験インフラを統合したチームへと向かっている様子を見てきました。AIの予測をいかに早く物理世界で検証できるか、その「実験閉ループ」こそが競争力の源泉になっている、と。では、そのループを力強く回すエンジン、すなわちAI技術そのものは、今どのような進化を遂げているのでしょうか。どうやら、ここでもいくつかの大きな潮流が見えてきたようです。
言葉のように分子を紡ぐ「化学言語モデル」
まず注目したいのが、分子を一種の「言語」として扱うアプローチです。私たちが日々使っているChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、単語の並びから次に来る単語を予測することで、自然な文章を生成します。実は、化学の世界でも分子構造を「SMILES」という文字列で表現することができます。このSMILESを文章に見立て、「この文字列の次に来るべき文字は何か?」とAIに予測させることで、全く新しい分子を設計しようというのが「化学言語モデル」の基本的な考え方です。
このアプローチが単なる理論にとどまらないことを示したのが、「TamGen」というモデルです。研究者たちは、このGPTライクなモデルに「結核菌の特定のタンパク質(ClpPプロテアーゼ)を阻害する」という条件を与えて分子を生成させました。その結果は驚くべきものでした。AIが設計した複数の候補の中から、実際に合成・検証したところ、最も優れた化合物は1.9 µMという強い阻害活性(IC50)を示したのです。
これは、化学言語モデルが広大な化学の空間から、特定の目的に合った有望な候補を高速で探索できる能力を持つことを実証した重要な事例と言えるでしょう。まるで優秀な編集者が、膨大な言葉の海から的確な表現を見つけ出してくるかのようです。
形を捉える「グラフトランスフォーマー(Graph Transformer)」
一方で、分子を単なる文字列として扱うだけでは捉えきれない情報もあります。それは、原子同士の繋がりや三次元的な「形」といった構造的な情報です。化学言語モデルが文章の「流れ」を読むのが得意だとすれば、これから紹介する「グラフトランスフォーマー(Graph Transformer)」のアプローチは、建築の「設計図」を読むのに長けている、と言えるかもしれません。
この技術は、分子を原子(点)と結合(線)で構成されるグラフ構造として認識し、どの原子がどの原子とどのように繋がっているかを直接的に学習します。これにより、化学的に無理がなく、実際に合成しやすい、より「構造的に妥当な」分子を設計できる可能性が高まります。
正直なところ、現場では「化学言語モデル」と「グラフトランスフォーマー」は競合する技術というより、役割分担をするパートナーとして捉えられているように感じます。例えば、まずは化学言語モデルでスピーディーに大量のアイデア(候補分子)を出し、その中から有望なものをグラフ系のモデルで構造的に精査し、合成可能性を評価する。このようなハイブリッドなワークフローが、探索の「速さ」と設計の「質」を両立させるための、現実的な答えになってきているのではないでしょうか。
生命の設計図を書き換えるLLM
AIの進化は、低分子医薬品という領域を飛び越え、さらに複雑な生命の設計図そのものにまで及んでいます。その最たる例が、Profluent社が開発したAI遺伝子編集ツール「OpenCRISPR-1」です。
これは、LLMを用いてゼロから設計された全く新しい遺伝子編集ツールであり、まさにAIが生命のプログラムを書き換える「言葉」を創り出した事例と言えます。自然界の進化の過程に縛られることなく、AIが膨大なタンパク質配列データから学習し、最適な機能を持つように設計したのです。
その性能は目覚ましく、ヒトの細胞を用いた実験では、既存の代表的な遺伝子編集ツールであるSpCas9と同等の編集効率を示しつつ、狙った場所以外を編集してしまう「オフターゲット」のリスクは大幅に低いことが報告されています。
さらに興味深いのは、Profluent社がこの革新的なツールをオープンソースとして公開し、研究や商用での利用を無償でライセンス提供している点です。これは、技術を独占するのではなく、コミュニティ全体の力でその可能性を検証し、発展させようという新しい戦略の現れかもしれません。
このように、分子生成の技術は、異なるアプローチがそれぞれに深化し、応用範囲を広げながら、全体として一つの大きなエコシステムを形成しつつあります。もはや単一の優れたモデルが全てを解決するのではなく、様々な技術を組み合わせる「組み合わせ戦」の時代が始まっているのです。
しかし、これほど強力な技術を手にしたからといって、創薬の成功が保証されるわけではありません。AIがもたらす「速さ」や「新規性」の先には、また別の、しかしもっと本質的な課題が横たわっているようです。次のセクションでは、なぜ「速さ」だけでは勝てないのか、成功の鍵がAIの“外”のどこにあるのかを探っていきたいと思います。
成功の鍵はAIの“外”にある:なぜ「速さ」だけでは勝てないのか?

これまでのセクションで、私たちは生成AIが分子生成の市場をいかに熱狂させ、資金の流れを変え、そしてTamGenやOpenCRISPR-1といった驚くべき技術を生み出しているかを見てきました。AIが創薬の「速さ」を劇的に向上させる、その可能性は疑いようもありません。しかし、ここで一度立ち止まって、冷静に問うてみる必要があると思うのです。速く走りさえすれば、本当にゴールにたどり着けるのでしょうか?
「失敗を早めるだけ」では意味がない
あるAI創薬企業のCEOが、非常に示唆に富む指摘をしています。「失敗を早めるだけではビジネスモデルにならない」と。多くの創薬AIスタートアップが苦戦する理由を分析したこの記事によれば、臨床試験で薬が失敗する主な原因は、実は「分子の設計が悪い(化学が遅い)」からではない、というのです。
ほとんどの失敗は、第II相臨床試験、つまり「本当に患者に効果があるのか?」を問われる段階で起こります。その根源にある問題は、多くの場合、化学(Chemistry)ではなく生物学(Biology)にあります。具体的には、
- そもそも狙うべき「ターゲット」の選定が適切だったか?
- その薬が効くはずの「患者」を正しく見極められていたか?
- 効果を測るための「バイオマーカー」は正しかったか?
といった、より根源的な問いです。AIがどれだけ高速で優れた分子を設計できたとしても、向かうべき方向が間違っていれば、それは単に間違ったゴールへ猛スピードで突き進んでいるに過ぎないのかもしれません。実際、AI設計薬として注目されたExscientia社のDSP-1181が第I相で開発中止となった事例は、AIが臨床の壁を自動的に乗り越えさせてくれる魔法の杖ではないことを物語っています。
Insilicoの成功を再解釈する
ここで、再びInsilicoの成功事例に立ち返ってみましょう。彼らのRentosertibが特発性肺線維症の患者で有望な結果を示したNature Medicineの論文は、単に「AIが速く分子を設計した」という話ではないように私には見えます。
彼らのアプローチの真髄は、AIプラットフォームを用いてターゲットの発見から分子設計、さらには臨床効果を予測するバイオマーカーの仮説までを一気通貫で繋げた点にあるのではないでしょうか。つまり、AIを単なる「分子設計ツール」としてではなく、「生物学的な問いに答えるための羅針盤」として活用したのです。成功の鍵は、AIの“中”にあるモデルの計算速度だけでなく、AIの“外”にある生物学的な問いと、それを検証する現実世界の実験とを繋ぐ設計思想にあった、と考えられませんか。
スタートアップと投資家が取るべき戦略
この気づきは、私たちに具体的な戦略的示唆を与えてくれます。AI創薬の世界で本当に価値を生み出すためには、AIの“外”にある3つの戦場で勝つ必要があるのです。
- 「実験閉ループ」の構築は最低条件
前のセクションでも触れましたが、AIの予測を高速で検証する物理的な実験インフラ(Wet Lab)は、もはや差別化要因ですらなく、競争に参加するための最低条件になりつつあります。資金がDeepCureのような自動合成プラットフォームを持つ企業に集まるのは、彼らがAIの仮説を現実世界で証明する力を持っているからです。投資家は、もはや「モデルの性能」だけでなく、その企業の「Wet Lab連携力」や「合成速度」を厳しく評価すべきです。
- 臨床PoC(概念実証)への最短経路を描く
AI創薬の価値は、最終的に臨床での成功によって証明されます。そのためには、初期段階から臨床試験の成功確率を高める設計が不可欠です。スタートアップは、有望なin vivo(動物実験)データや、効果を予測できるバイオマーカー候補を早期に提示することが求められます。投資家にとっても、候補化合物の臨床PoCの可能性こそが、最も重要な評価ポイントとなるでしょう。
- データ品質と規制対応という「見えざるインフラ」
AIの予測精度は、学習データの質に大きく依存します。しかし、高品質なデータは希少であり、その管理と活用能力が企業の生命線となります。また、AIが生成した分子を知的財産としてどう守るか、規制当局にその有効性と安全性をどう説明するか(説明可能性、XAI)といったガバナンス体制の構築は、見過ごされがちですが、長期的な成功を左右する重要な要素です。
結論:AIは地図であり、旅そのものではない
生成AI×分子生成の旅は、まだ始まったばかりです。Insilicoの臨床成功は、AIが私たちに新しい世界の広大な地図を与えてくれたことを証明しました。しかし、その地図を手に、どの山に登り、どの川を渡るのかを決めるのは、深い生物学的な洞察です。そして、実際にその道のりを踏破するには、実験という名の堅牢な乗り物と、規制という名のコンパスが不可欠なのです。
これからの10年、この領域で本当に成功を収めるのは、単に最速のAIを持つ者ではなく、AIの力を借りて最も賢明な問いを立て、それを現実世界で粘り強く証明し続けた者になるでしょう。
さて、あなたの組織では、AIという新しい地図を手に、次にどのような問いを立てますか?

調査手法について
こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。
調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。
また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。
ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。
また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。
市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai
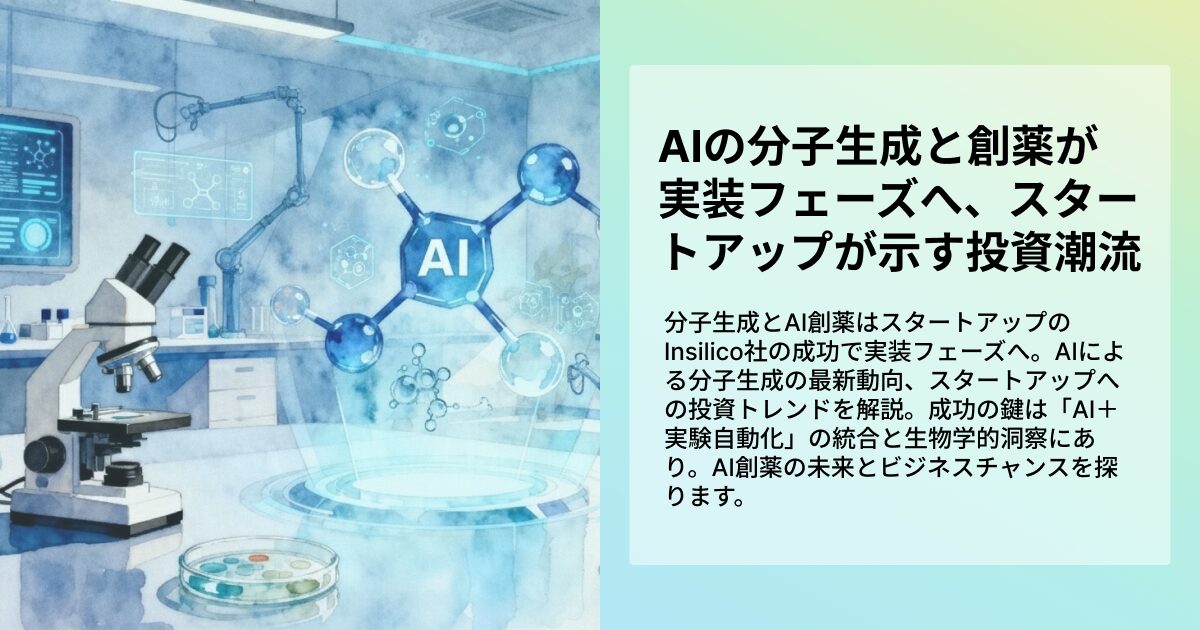





コメント